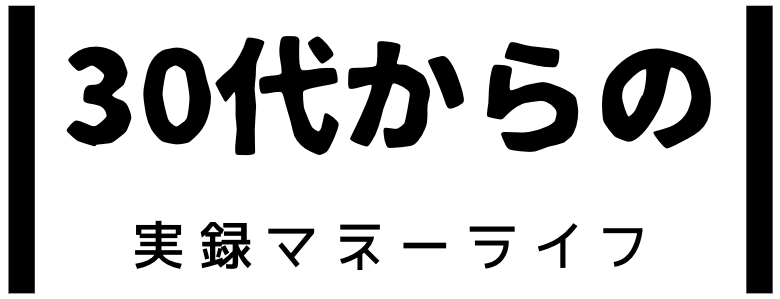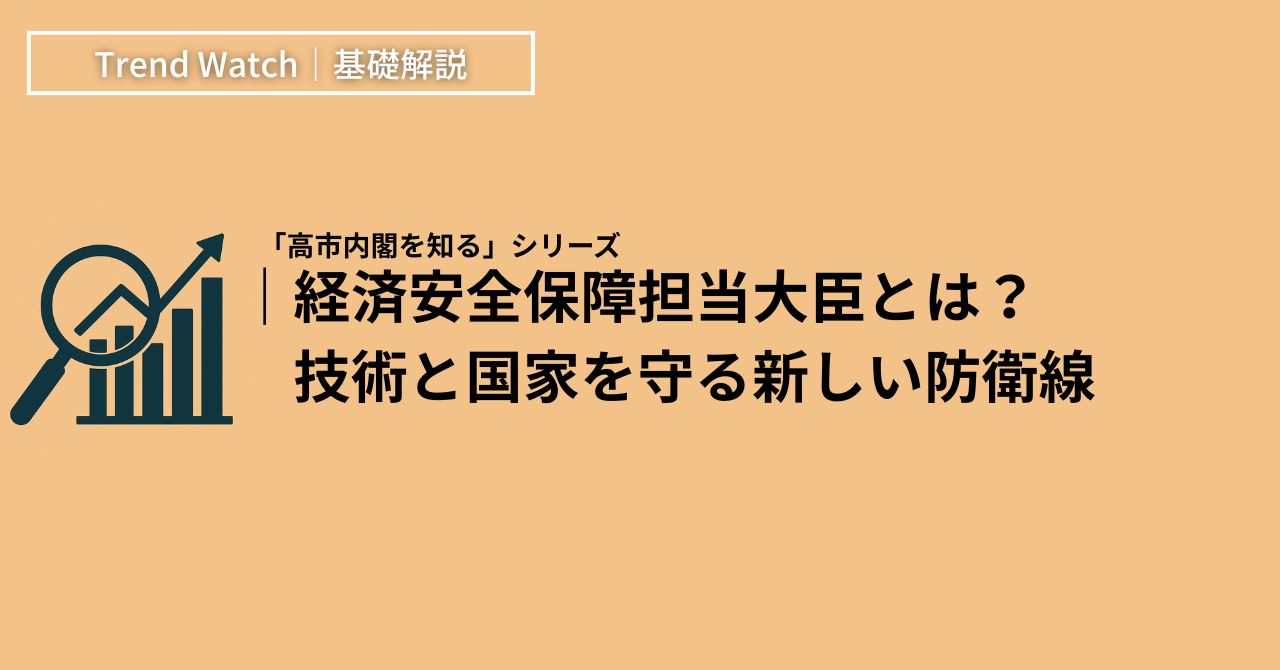経済と安全保障――。 かつては別々の分野だったこの2つが、今や世界的に一体化しつつあります。 この潮流の中で誕生したのが、経済安全保障担当大臣という新しい役職です。
本記事では、経済安保担当大臣が何を担い、なぜ今このポジションが重要視されているのかを、 高市内閣の動きを踏まえてわかりやすく解説します。
なぜ「経済安全保障」が必要なのか
近年、国際情勢は急速に変化しています。 特に、半導体やレアアースなどの重要資源・技術をめぐって、国家間の競争が激化しています。
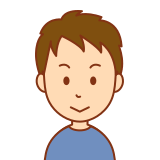
つまり、経済が安全保障の一部になってきてるってことですか?
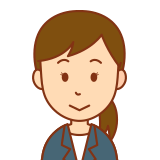
そうです。たとえば半導体が他国から入らなくなると、
スマートフォンも自動車も作れません。
経済活動そのものが安全保障のリスクに直結する時代なんです。
このような背景から、日本政府は経済安全保障推進法を制定し、
重要技術やサプライチェーンを守るための枠組みを整備しました。
その司令塔が「経済安全保障担当大臣」です。
経済安保担当大臣の主な役割
経済安全保障担当大臣は、国家の経済基盤を守るために、以下のような任務を担います。
- ① 重要物資・技術の確保: 半導体、電池、医薬品などの安定供給を確保
- ② 研究開発の保護: AI・量子技術などの機密研究を国家レベルで保護
- ③ サプライチェーンの多角化: 特定国依存を減らし、国内生産を強化
- ④ 民間企業との連携: 官民一体でリスクを分散し、経済安全保障を推進
経済安保の要は「技術の確保」と「依存リスクの分散」。 つまり、“目に見えない安全保障”を守る仕事なのです。
高市内閣における経済安保の位置づけ
高市内閣では、経済安保担当大臣に小野田紀美氏が就任しました。 彼女はテクノロジーやスタートアップ支援にも理解があり、 「防衛」と「経済」の両輪を強化する象徴的な人事といえます。
特に注目されるのが、経済安保とデジタル政策の連動です。 データ保護・通信インフラ・AI倫理など、境界線の曖昧な分野を横断的に監督する必要があります。
このように、経済安保はもはや“防衛省だけでは守れない安全保障”。 各省庁をつなぐハブとして、経済安保担当大臣の存在感は今後さらに高まるでしょう。
日本の「新しい防衛線」は、技術とサプライチェーン
従来の安全保障が「軍事力」中心だったのに対し、 経済安保は「技術力」と「供給網(サプライチェーン)」で国を守る発想です。
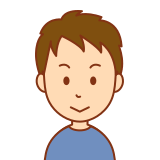
軍事じゃなくても、経済で国を守るって発想なんですね。
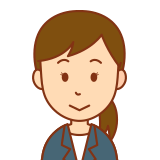
ええ。もしサプライチェーンが止まれば、経済も防衛も止まります。
経済安保は、まさに“平時の防衛”なんです。
経済を守ることは、国を守ること。
この新しい価値観こそが、21世紀型の安全保障の基礎になっています。
まとめ:経済安保は“未来を守る政策”
- 経済と安全保障の一体化が進み、国家の新しい防衛線となっている
- 半導体・AI・サプライチェーンが中心テーマ
- 高市内閣では小野田紀美氏が旗振り役として注目
ニュースで「経済安保」という言葉を見たら、 それは単なる経済政策ではなく、“技術で国を守る戦略”だと考えてください。
🗓️ 次回予告|高市内閣を知る④
テーマ: デジタル大臣とは? 行政DXとサイバー防衛の最前線
👉 次の記事はこちら
この記事は「高市内閣を知る」シリーズ第3回です。
👉 シリーズ一覧はこちら