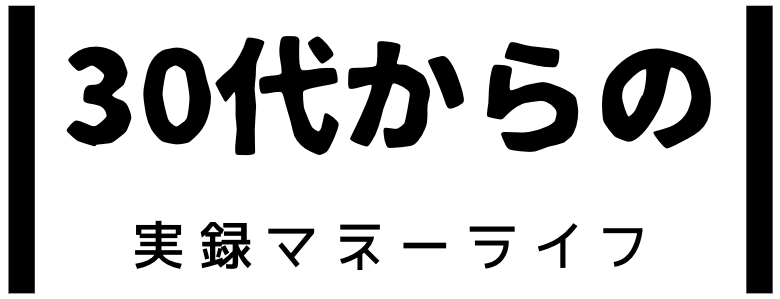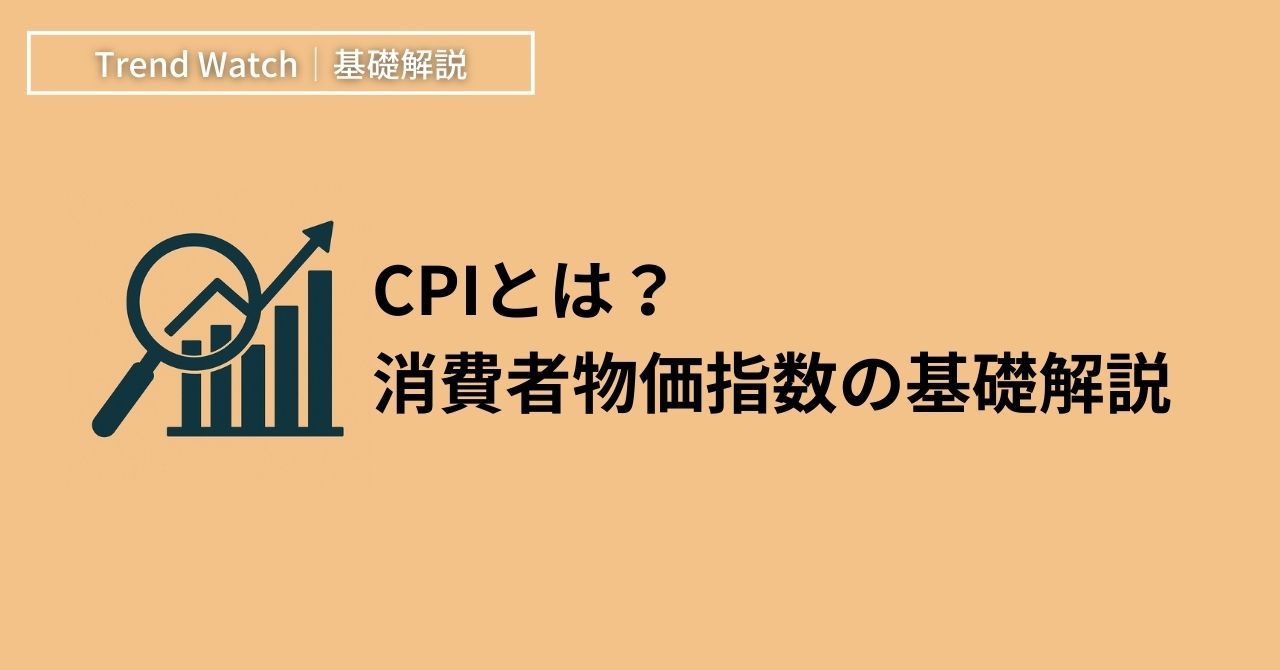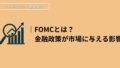導入
「最近、物価が上がっている気がする…」
そんな生活実感を数値化して示してくれるのが CPI(消費者物価指数:Consumer Price Index) です。
家計、企業、そして金融政策まで幅広く使われる基本的な経済指標。初心者でもわかるように解説します。
CPIの定義
- CPI(消費者物価指数) とは、一定期間のモノやサービスの価格の変動を数値化した指標。
- 総務省統計局が毎月発表。対象は食料、住居、光熱費、交通費など。
- 「生活費の上昇率」を示すため、家計の実感に近い数字として注目されています。
CPIが注目される理由
- 家計への影響
生活必需品価格の変動を把握できる。インフレが進むと「実質賃金」が下がることも。 - 金融政策との関係
日本銀行はCPIを参考に「物価安定目標(2%)」を設定。利上げ・利下げ判断の根拠に。 - 投資や市場への影響
CPI上昇 → 利上げ観測 → 円高株安
CPI低下 → 利下げ観測 → 円安株高
といった形でマーケットに直結します。
CPIの読み方のポイント
- 総合CPI:すべての品目を含む
- コアCPI:生鮮食品を除いたもの(日本の代表値)
- コアコアCPI:生鮮食品+エネルギーを除いたもの(基調的な物価動向を把握)
👉 ニュースで「CPIが◯%上昇」とあれば、まずはコアCPIを指していると考えて良いでしょう。
例:生活への影響
例えばコアCPIが前年比+3%なら…
- スーパーの食料品、光熱費、外食が値上がり傾向
- 賃金が2%しか伸びていない場合 → 実質賃金はマイナスに
つまり「給料は増えても生活が楽にならない」という現象が起こります。
まとめ
- CPI=物価の動きを示す基本指標
- 家計、日銀政策、投資に直結する
- ニュースで数字を見るときは「コア」「コアコア」に注目